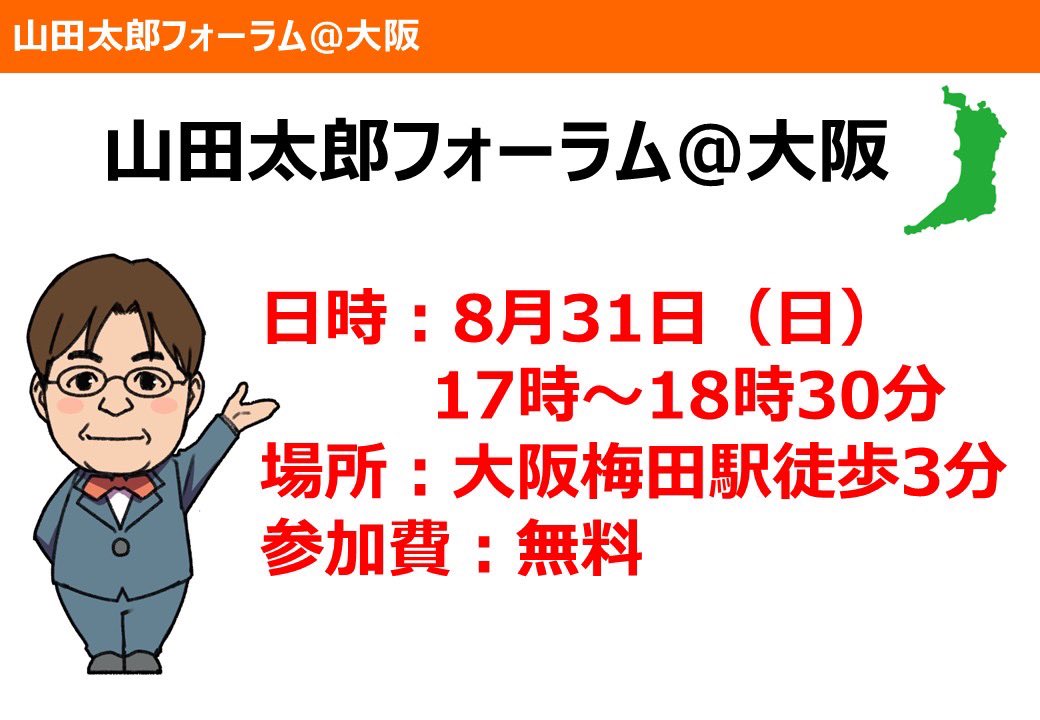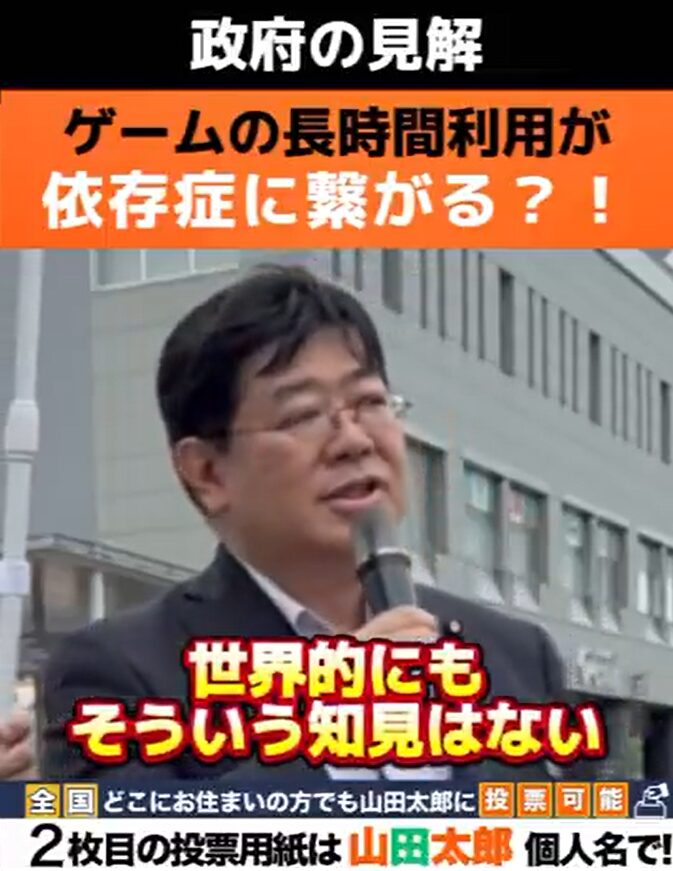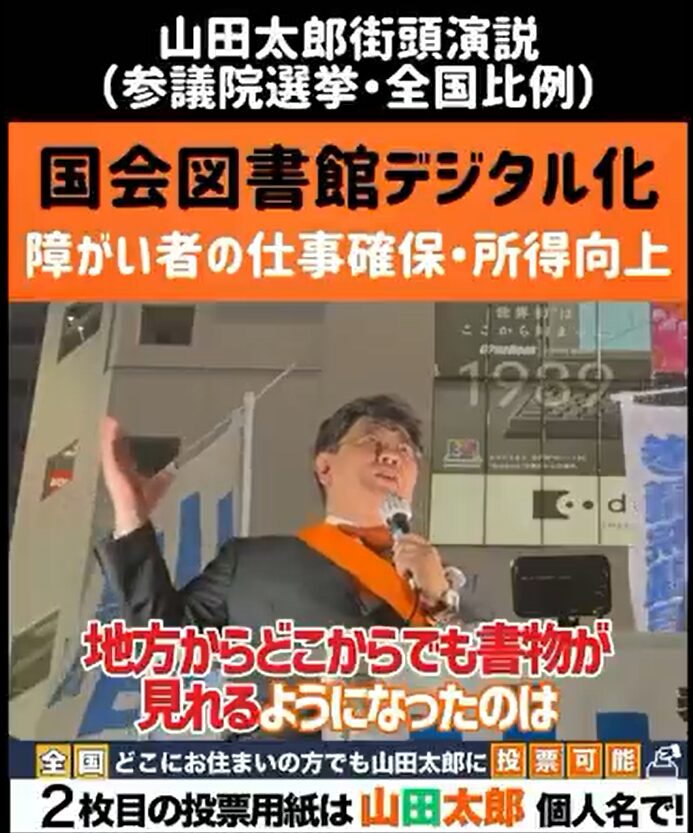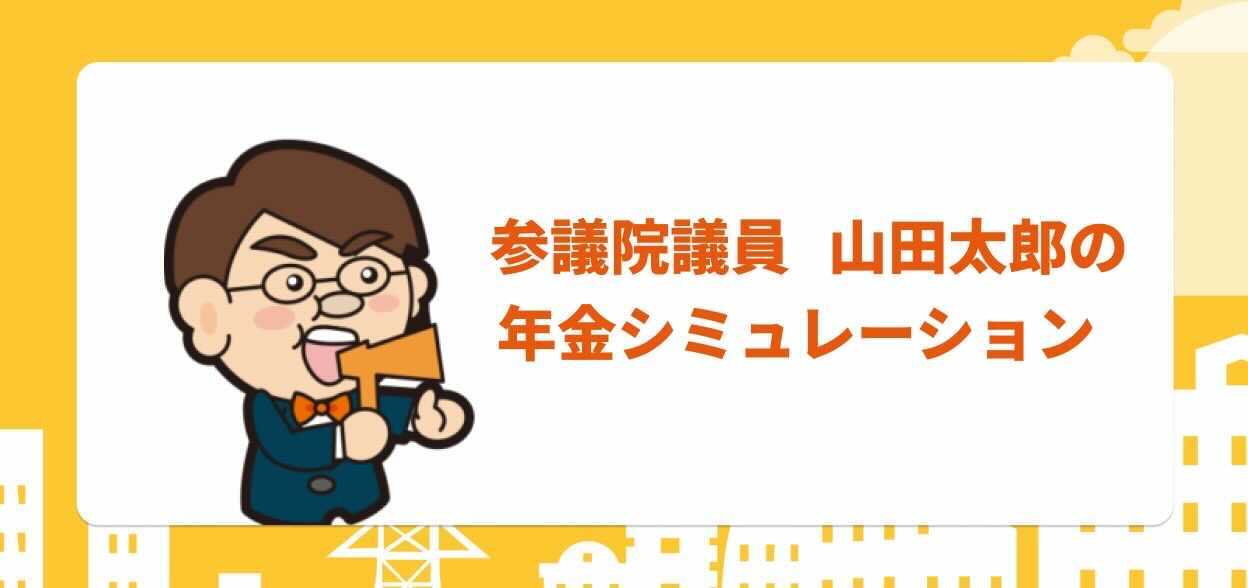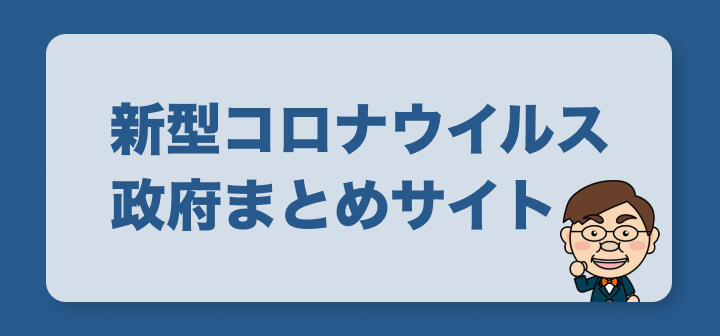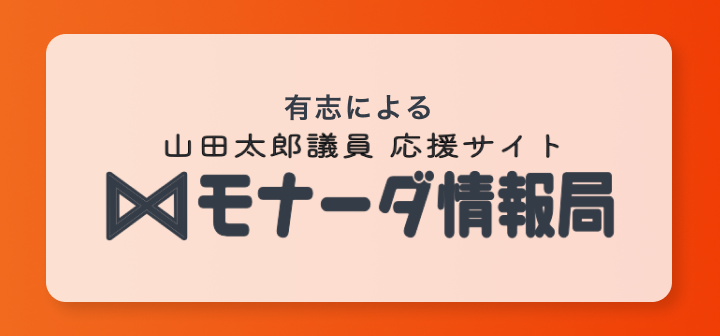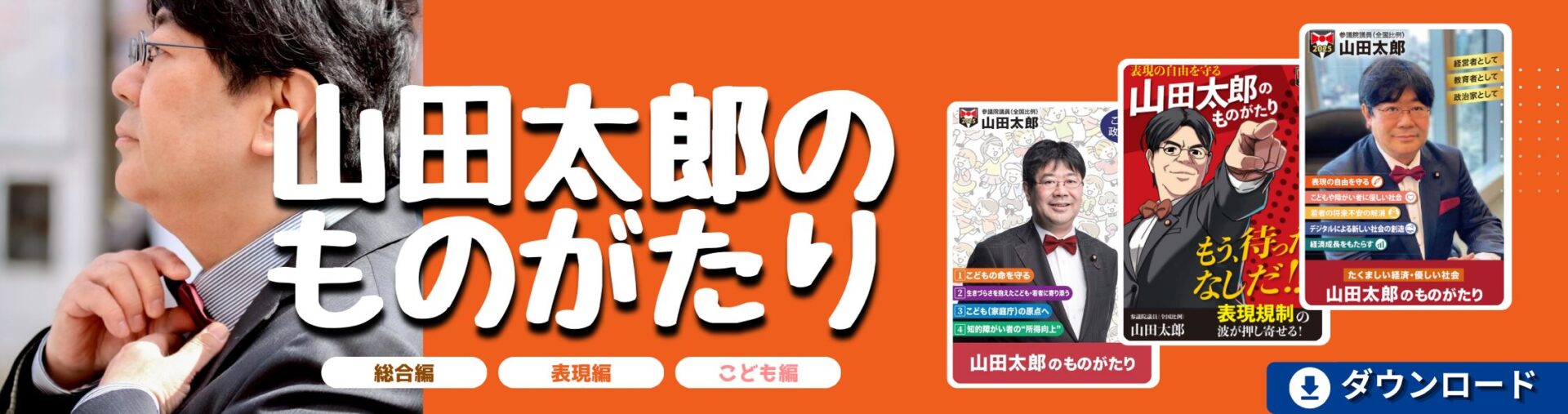2025.5.20
金融庁・経済産業省へガイドライン策定等を依頼
決済アプリの残高がわずかの間で消えるとの報道。 クレカ問題と同様、プラットマーに対して一定の規律が必要と考えています。私は、デジタル時代の決済として、ユーザーの利便性向上のため、キャッシュレス決済をサポート。デジタル大臣政務官時代には、国に納付する手数料等のキャッシュレス化も推進。ただし、それらは安全・安心に利用できることが前提です。利用者保護の観点から問題があるのではないかとの見方から関係について行った質問とその回答は以下のとおりです。
A(金融庁)資金決済法上は問題がない。
Q 6ヶ月以上利用実績がないので閉鎖したアカウントの残高を「没収」することは適法なのか? 6ヶ月以上利用実績がない場合、ただちにアカウントを閉鎖できるとの規約は、「相手方の利益を一方的に害すると認められるもの」(548条の2第2項)として無効ではないのか?
A(金融庁) 548条の2第2項に該当するかどうかは判断する立場にない。一社問題であり、ただちにキャッシュレス決済の推進が阻害されるとは考えていない。
法省務からは、548条の2第2項によって有効とされる可能性がある旨、消費者からは、消費者の利益を一方的に害する条項に該当する可能性がある旨、回答もありましたが、最終的に利用者が裁判を起こして、裁判によって判断がなされることのこと。 資金決済法は、「資金決済に関するサービスの適切な実施を確保し、その利用者等を保護する」ことを目的として検討しております(1条)、事業者による和解から利用者を保護するために供託制度を設けている限り(14条以下)、残高の有効期限は定額で自由に決められると言っているが金融庁の見解。
利用者保護の観点からは、悩みが解消時効の期間(5年)よりも短期間の残高の有効期限を定める場合は、不意打ちになる場合が多く、かつ、利用者の権利を不当にするものであるため、規律を設ける必要はないのでよい。金融庁や経済産業省には、我が国での残高の有効期限を定めることに関するガイドラインの策定を初め検討を依頼しましたが、キャッシュレス決済に関して利用者を保護する制度化の検討も進める必要があると考えております。