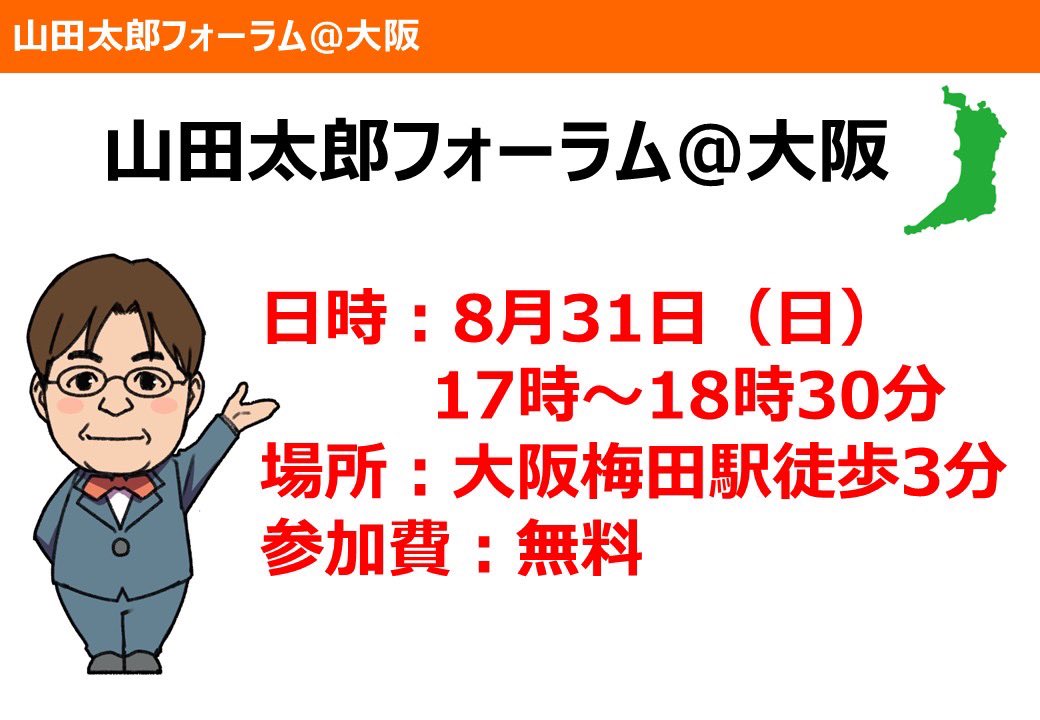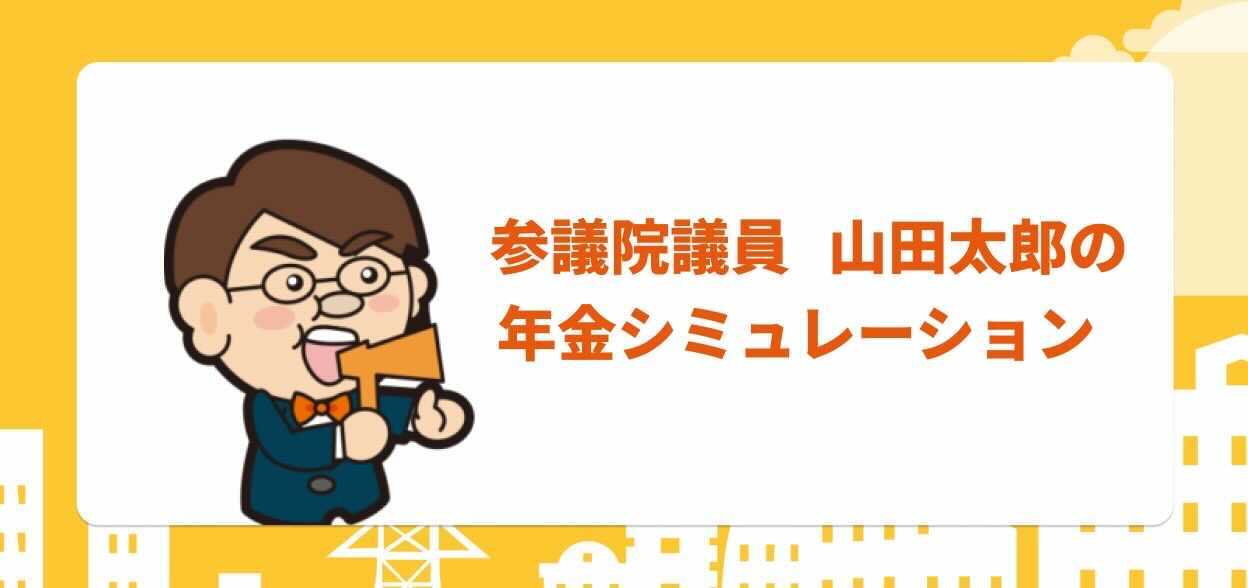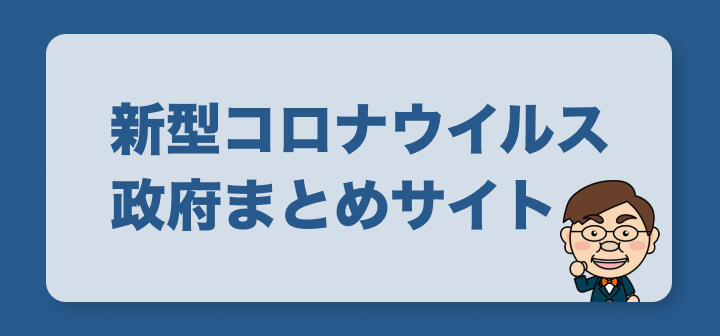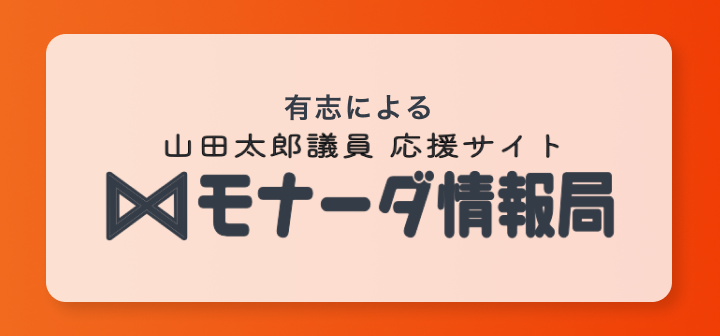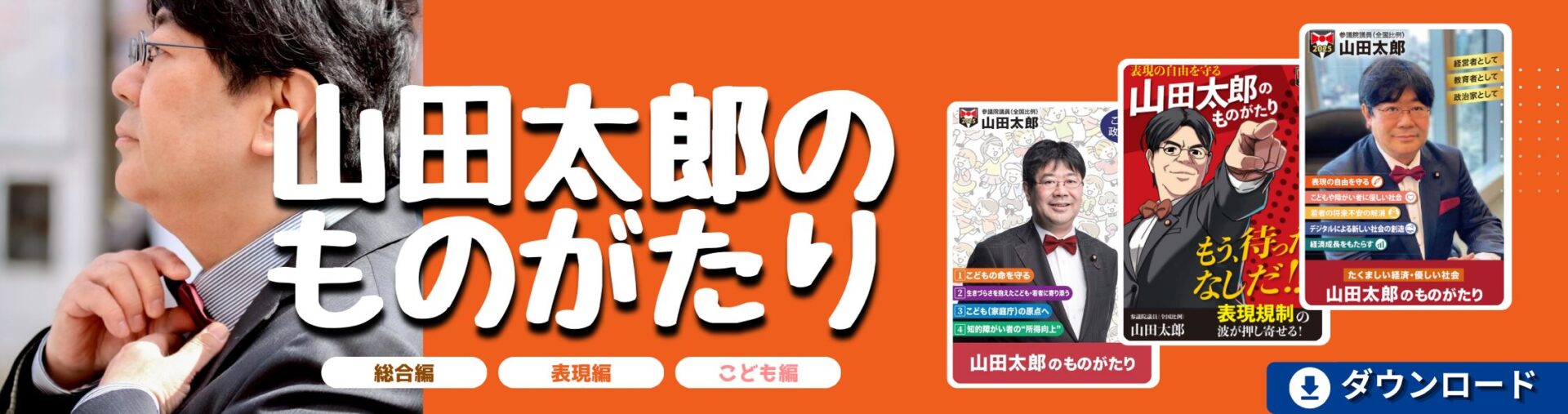2025.4.1
情報プラットフォーム法について
情報プラットフォーム法が本日4月1日施行。情プラ法は、「SNS規制である」、「表現規制である」といった意見が散見。しかし、プロバイダの恣意的な自主的削除から表現の自由等を保護する目的もある。詳細を策定に関与した私から説明。
情プラ法の目的は、①権利侵害情報から名誉やプライバシー、著作権や商標権等を保護すること、②プロバイダの恣意的な自主的削除から表現の自由等を保護することの2本立て。

情報流通プラットフォームであるSNS事業者等に規律を課す法律ではありますが、それは上記2つの目的のため。特に、この法律は、表現の自由を守る目的の側面もある点について、まだまだ理解が不十分な状況です。 そもそも、もともとのプロバイダ責任制限法=プロ責法(情プラ法の名称が変わる前の法律名)では、投稿の削除について何の規律も定めていないという問題がありました。 投稿の削除は、契約、利用者規約、自社の方針に照らして条理・法令に基づき義務があると判断された場合、不適切と判断した場合になされるはずでした。 しかしこの自主的削除については、根拠や理由が分からなず勝手に、また突然知らない間に行われていて、プロバイダの恣意的なものが目立つようになり、表現の萎縮につながっているとの指摘がありました。

そこで、プロ責法を改正して情プラ法を制定する際、表現の自由を保護する観点から、自主的削除については、「自ら定め、公表している基準に従う場合に限り」できるという規律を設けました(26条1項柱書)。 一方、情プラ法は、投稿の削除について、「実体法上の新たな根拠」を定めるものではなく、その意味では表現規制を行うものでもありません。 なお、情プラ法では、プロ責法にはなかった罰則が設けられましたが、原則として、手続上の義務、規律に違反(勝手に基準も通知もなく投稿を消した等)したとして総務大臣から勧告がなされ、その勧告に正当な理由がなく応じなかったとして措置命令が出たにもかかわらず、当該措置命令に違反した場合のもので、法の実効性を担保するために必要最小限の定めと言っていいと思います。 また、運用次第で表現の自由が制限される不安は残ってますので、運用を注視していくことは必要です。 そこで、様々な不安の声も受け、情プラ法施行にあたって上記のまでの説明に追加して、以下の点を改めて政府に確認しています。 ●情プラ法は、表現の自由の萎縮つながる対応を求めるものではない。 ●親告罪である著作権侵害について、「被侵害者以外の者による第三者の削除申出」がなされても、それは違法かどうかは判断できず、それだけで削除はできない。 実効的な侵害情報対策がなされながらも、一方、表現の自由が絶対に守られる様、情プラ法の運用について引き続き注視し対応ていきます。